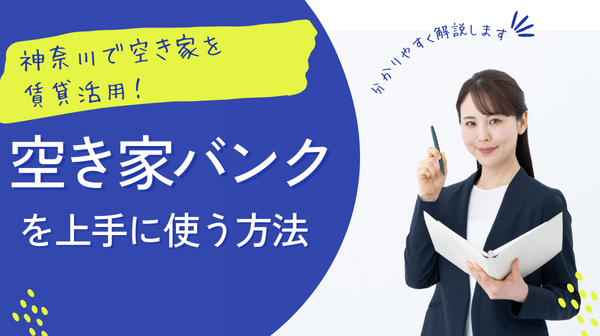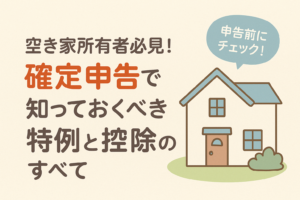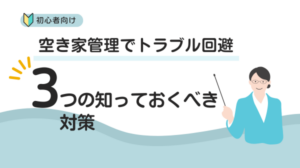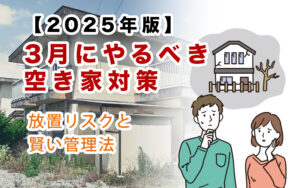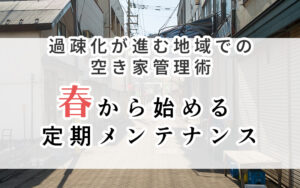神奈川で空き家をお持ちのオーナー様へ
空き家バンクを活用して、放置している空き家を賃貸物件として活用してみませんか?
この記事では、空き家事情や空き家バンクの仕組み、実際に賃貸運用する際のポイントなどを
分かりやすく解説します。
空き家事情と賃貸ニーズ
空き家率の現状
2024年4月末に総務省が発表した「住宅・土地統計調査」によると、
日常的に人が住んでいない空き家の数は900万戸となり、前回2018年の調査から51万戸
増え過去最高となりました。
高齢化や人口減少の影響を受け、地方部を中心に空き家が年々増加しています。
放置された空き家は、防災面のリスクや景観の悪化など、さまざまな問題を引き起こす可能性があり、
地域全体の課題として対策が急がれています。
県や市町村では、空き家バンクの整備や改修補助制度などを通じて、空き家の賃貸や売買を後押しする
仕組みを進めています。

神奈川県でも地域によって空き家率に差が
神奈川県内における空き家率は地域によって大きな差がみられます。
【総務省 令和5年住宅・土地統計調査】市町村別空き家率
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/14815/sonota_akiyaritsu.pdf
県西部の山間地域や、三浦半島など過疎化が進む地域では空き家率が高い傾向にあります。
これらの地域では若年層の転出や高齢化が進むことで空き家が増加しています。
横浜や川崎などの都心部や、湘南エリアで都心へのアクセスが
良い地域では賃貸のニーズが依然として高い状況です。
空き家を所有されている方は自身の物件が所在する地域の特性を把握し、
賃貸ニーズがあるのかを見極めることが重要です。
都心へのアクセスが良い環境であれば、賃貸物件として活用することで
安定した収入を得られる可能性があります。
一方、過疎化が進む地域では、賃貸ニーズが低い場合もありますが、地域おこし協力隊
の誘致や、移住希望者向けの物件として活用するなど、地域の状況に合わせて検討しましょう。
賃貸ニーズが高いエリアの傾向
神奈川県内で、賃貸ニーズが高いエリアとしてはまず、横浜市や川崎市といった
政令指定都市が挙げられます。
東京都心へのアクセスが良く、首都圏のベッドタウンとしても機能しており、
その利便性の高さが人気の要因です。
特に駅からのアクセスが良い物件や、スーパー、ドラッグストアなど、
生活利便施設が整っている物件は支持されています。
通勤、通学に便利なエリアは今後も継続的なニーズが見込まれます。
その他、注目されるエリアは湘南エリアです。
温暖な気候と美しい海岸線が魅力で観光地としてだけでなく、移住地としての価値も
高まっています。
近年では、リモートワークの普及により、都心から湘南エリアへと移住する人が
増加し、それに伴い賃貸需要も拡大しています。
さらに箱根や鎌倉といった観光地周辺エリアも一定の賃貸ニーズを維持しています。
これらの地域では旅館やホテルなど観光業関連施設で働く人の居住ニーズに加え、
セカンドハウスや別荘としての利用を想定した高級賃貸への需要も見られます。
観光スポットに近い立地や、温泉付き物件など特別感のある施設を備えた
住居は特に高い人気を誇ります。
空き家バンクとは?仕組みと流れについて
空き家バンクとは
「空き家バンク」とは、自治体などが運営する空き家の売買や賃貸を希望する所有者と、
空き家を利用したい人をつなぐ仕組みのことです。
近年、空き家問題の対策として、特に地方自治体が積極的に導入しており、
「移住者向け支援制度」や「改修費補助」などとセットで提供されるケースもあります。
物件登録から賃貸に出すまでの流れ
空き家バンクへの物件登録から、賃貸開始までの流れは、一般的に以下のようになります。
1. 空き家バンクに登録・申請
空き家の所有者が自治体に空き家バンクへの登録申請をする
→物件の所在地、築年数、間取り、写真、所有者の情報などを提出します
2. 自治体による現地確認・調査
自治体の職員または委託業者が物件を現地調査
→建物の安全性、劣化状態などをチェック
3. 空き家バンクのサイト等で物件情報を公開
調査後、登録が認められた物件は自治体の「空き家バンク」ページに掲載される
4. 利用希望者からの問い合わせ
空き家を借りたい人(移住希望者など)からの問い合わせ
→内見の調整や所有者との面談が行われます
5. 交渉・契約
条件が合えば所有者と、借り手との間で賃貸契約を締結します。
→自治体は基本的に「紹介のみ」で、契約自体は当事者同士か、不動産会社を
通じて行う場合が多いです。
6. 利用開始
賃貸契約が完了し、入居者が物件を利用し始めます
→必要に応じて、不動産会社や建築業者などの専門家と連携することも重要です。
賃貸運営における注意点と対策
空き家を賃貸物件として活用することは、収益化や、地域活性化につながる有効な手段ですが、
運用にはさまざまなリスクや注意点が伴います。
ここでは、賃貸運用を成功させるために押さえておきたい注意点と対策を解説します。
物件の老朽化と改修
空き家の賃貸運用において最も重要な注意点の1つが物件の老朽化です。
長期間使用されていなかった家屋では、屋根や外壁の劣化・水回り設備の故障・シロアリ被害
・カビなど、さまざまな問題が発生している可能性があります。
これらを放置したまま入居者を迎えると、クレームや早期退去につながるだけでなく、
安全面でのトラブルにも発展しかねません。
賃貸開始前には、専門業者による建物診断を行い、必要な箇所の改修を徹底しましょう。
特に屋根や外壁の防水性、耐震性、給排水設備の確認は必須です。
また、電気、水道など専門的な知識や技術が必要な作業は必ず専門業者に依頼するように
しましょう。

入居者とのトラブル防止策
賃貸経営において、入居者とのトラブルは避けて通れません。
代表的な例として、家賃滞納・騒音・ゴミ出し・無断退去などがあります。
これらを未然に防ぐには契約内容を明確にし、入居者との間で合意した内容を詳細に記載し、
双方が内容を理解したうえで、契約を締結することが重要です。
近隣住民との関係構築
賃貸運用では、入居者だけでなく地域住民との関係性も重要です。
特に空き家が長らく放置されていた地域では、新しい住民との間に摩擦が生まれる可能性が
あります。
事前に挨拶をしておく、地域ルールを確認するなど地域とのコミュニケーションを大切にする姿勢が
円滑な運営につながります。

税金や維持費について
空き家を賃貸として活用する場合、税金や維持費が発生します。
これらの費用を事前に把握し賃貸収入のバランスを考慮することが安定した賃貸経営を行う上で
非常に重要です。
必要経費には、修繕費をはじめ、損害保険料、減価償却費、管理費などが含まれます。
また、現状回復費や、入退去時のクリーニング費用も見込んでおくべきです。
空き家の活用事例
ここでは「空き家活用の実際の事例」をいくつかご紹介します。
空き家をどのように再生し、地域や人の役に立つ形に変えていったのかを
賃貸だけでなく、多様な視点からまとめました。
地域のシェアオフィスに変身 (長野県・松本市)
空き家をITワーカー向けのコワーキングスペースに改修。
Wi-Fi、会議室などを整備し、フリーランスや地域の起業家が集まる場所に。
→空き家が「地域の交流拠点」として再生。
テレワーク需要の高まりとマッチし地方再生の一環にも。
ポイント:テレワーク対応×企業支援×地域活性化

カフェ兼コミュニティスペース(京都府・京丹後市)
古民家を改修して、カフェ+多目的スペースとして活用
移住者がオーナーとなり、地元野菜を使った軽食を提供。
ワークショップや地域イベントも開催し、高齢者と若者が交流する場に。
ポイント:飲食+交流の複合利用×空き家リノベ×地域の拠点

短期滞在・観光用の民泊施設(大分県・由布市)
使われていなかった平屋の空き家を簡易宿泊所(民泊)として再活用。
観光地に近く、旅行者向けに「田舎暮らし体験付き宿泊プラン」を提供。
外国人観光客向けにも好評。
ポイント:観光資源と連携×民泊許可×空き家を収益化

若者のシェアハウス(東京都・青梅市)
広めの空き家を数人で使えるよう、間取りを調整し、学生や若者向けシェアハウスに。
一人当たりの家賃を抑えながら、地域の人との交流や、就農体験の場としても運営
ポイント:複数人利用×家賃調整×若者支援・地域交流

まとめ
今回は空き家を賃貸活用する場合をご紹介しましたが、空き家活用の可能性は無限大です。
「住まい」としてだけではなく、地域資源としての使い道も豊富です。
物件の特性や立地を見極め、「誰に」どのように使ってもらいたいかを
考えることが大切です。
活用の第一歩は「情報を整理すること」からです。
物件の状態は?・立地の強みは?・賃貸?売却?・改修して別用途?・自治体の補助制度は使える?
これらを一緒に考えることで空き家は新たな可能性を持ち始めます。